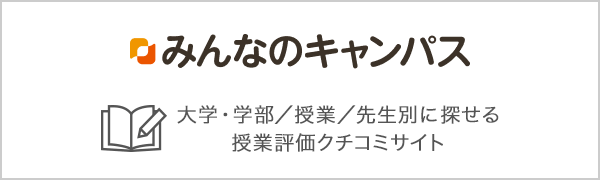-
設問:学生時代を振り返り、最も自ら考え周りを巻き込み行動出来たと思う場面を思い出し、その時のことを以下の質問に沿って記入してください。
・そのときの状況を記入してください。その状況下において、どのような課題がありましたか?〇〇の代表兼選手としての活動です。全国大会出場を目標とする中で、初めは楽しんでいれば強くなれると安易な考えで臨んでいました。結果、2年次に出場した関東インカレで惨敗し、自分を変えるきっかけを得ました。
その大会後私はチームの代表となりましたが、成績でチームを引っ張れない代表という肩書にプレッシャーを感じていました。もう一つの壁として、〇〇の種目の1つであるスイムの練習場所の確保に頭を抱えました。私は3種目の中でも特にスイムを苦手としており、スイムの練習は必須でした。しかし、練習場所となるはずの大学のプールが改修工事により使えず、私だけでなくチームとしても泳ぐ場所の確保に苦慮していました。チームのまとまりを維持するためにも、この課題を次の代に持ち越さないよう案を練っていましたが、学生特有の金銭的な問題もあるため、かかる費用も考慮に入れる必要がありました。
-
設問:あなた自身がとった行動を具体的に記入してください。(400文字以内)
設問1で述べさせていただいた課題に対して、一つ目の実力が伴っていないながらの代表としての役割として、実力で引っ張る役割は仲間に任せ、私は実力がないからこそチームを鼓舞して盛り上げる側に徹しようと考えま
した。そのために、私は個人練習だけでなく、毎週チームとして行われる練習には、練習場所までロードバイクで片道50kmかかろうと全て参加しました。二つ目の課題であった、チームとしての泳ぐ場所の確保に関しては、私1人では対処することの難しい問題でした。しかし、〇〇を通してできた繋がりをもとに、代表として他大学の学生に協力を仰ぎ、プール施設を借りたいという考えを伝えました。その結果、協力して合同で、年4回行われるスイミングスクール主催の大会役員をボランティアとして引き受ける代わりに、プール施設を格安の月に当たり1人1000円で平日の朝いつでも泳がせていただく話を取り付けることができました。
-
設問:それは、成功しましたか?その結果、どのようになりましたか?(400文字以内)
これまでの経験を通して、確実な自己成長と、組織の中心として動いたことで大きな2つの成功体験を得ることができました。一つ目の自己成長という点で、私は今年全国大会出場は惜しくも叶いませんでした。しかし、仲
間の協力も得ながら苦手なスイム練習環境を整えたことで、これまで週1回の練習を4回に増やしました。その成果として、大会でのスイムの記録を3分以上縮めることに成功しました。そして、全体順位も昨年関東大会での104位から、今年73位と大幅に順位を上げ来年への自信に繋げることができました。二つ目の組織の中心としての役割では、我々は全国大会出場者数を昨年2名から今年6名以上にする目標を立てました。結果スイムの練習環境も整ったことで、8名の全国大会出場とチーム目標を達成することができました。個人としての結果は出なかったものの、組織の中心としての活動により責任感が醸成され、チームに貢献する喜びを得ました。


![[26卒]インターン体験記投稿キャンペーン](/contents/nikki/config/rightnavi/special/img/20181004_120x120.png)
![[26卒]本選考体験記投稿キャンペーン](/contents/nikki/config/rightnavi/special/img/20240110_120x120.png)

![[27卒]みんなのインターン人気企業ランキング](/contents/nikki/config/rightnavi/special/img/20210408_120x120.jpg)
![[27卒]みんなのIT業界就職人気企業ランキング](/contents/nikki/config/rightnavi/special/img/20210409_120x120.jpg)