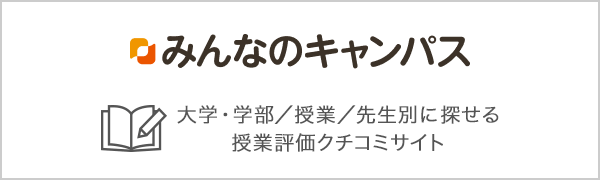-
設問:(1)当社インターンシップに期待すること、(2)インターンシップで取り組んでみたいテーマをお書きください。
(1)貴社のインターンシップでは、日本企業や日本社会が抱える都市・インフラ・防災に関わる課題の解決を通して、日本のプレゼンス向上に寄与する事業創出の過程を体験してみたいと考えている。 私は大学院で都市
計画学を専攻しており、地方都市の過疎化と東京一極集中、インフラ業界の人材不足、国土強靭化に向けた防災設備投資の不足など、日本の都市の現状について様々な問題意識を持っている。 貴社はこういった問題の実態把握と解決に向けて、幅広い領域でのリサーチ・コンサルティングを展開している。そのため、その具体的なプロセスを体験することで、その業務内容ややりがいへの理解を深めつつ、結果的に自身の成長にも繋げたいと考えている。 (2) インターンシップで取り組んでみたいテーマは、官民の防災インフラ投資の推進である。近い将来、南海トラフ巨大地震や首都直下地震により、日本の中でも都市機能や人口が集中する地域が被災し、ひいては日本の国家機能が根底から揺らぐ可能性も予想される。そのような国難に対する強靭性を高めるために積極的な投資を行うことは、将来の日本を救うための鍵になると考えている。よって、自身が強い課題観を持っているこの問題をコンサルティングのテーマとして扱ってみたいと考えている。
-
エントリーシート記入時に注意した点やアドバイス
結論ファーストを意識しながら、情報量のバランスが多く、少なくなりすぎないように意識して書いた


![[26卒]インターン体験記投稿キャンペーン](/contents/nikki/config/rightnavi/special/img/20181004_120x120.png)
![[26卒]本選考体験記投稿キャンペーン](/contents/nikki/config/rightnavi/special/img/20240110_120x120.png)

![[27卒]みんなのインターン人気企業ランキング](/contents/nikki/config/rightnavi/special/img/20210408_120x120.jpg)
![[27卒]みんなのIT業界就職人気企業ランキング](/contents/nikki/config/rightnavi/special/img/20210409_120x120.jpg)